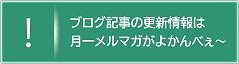( 香水工場の )
香る生活
ココアバター
ココアバターとは、ココアやチョコレートの原料である「カカオ豆」に含まれる脂肪分から精製された固形オイル。
熱帯に生育する「カカオの木」には、大きな「カカオの実」が実ります。
「カカオの実」には「カカオ豆」が含まれます。つまり「カカオ豆」は「カカオの実」の種(タネ)です。
この種には豊富な脂肪分や食物繊維が含まれているそうです。カカオ豆を水に浸けて発酵させ種の皮と胚芽を取り除いてすりつぶした固形状にしたものが「カカオマス」になります。
カカオマスは「チョコレート」や「ココア」(ココアパウダー)の原材料です。同時に「ココアバター」が採れます。
なぜ「カカオ」(Cacao)が「ココア」(Cocoa)というネーミングに変化するか不明です。「カカオバター」でもよさそうですが、なにか理由があるのでしょう。
私は、街に出たときハーブ・野草のお店や、手作り化粧品原料を販売しているお店にぶらりと入ることがあります。先日御徒町を歩いていてぶらりと入ったお店でココアバターを見つけました。
ココアバターは食べ物の原材料ですが、そこでは「化粧品原料のコーナー」で販売されていました。
ハンドクリームか練り香にしてみるか、と手に取ってみるとココアバターはクリーム色。
「チョコレート色でない」
ところで、「バター」とはもともと牛乳から採れる動物性の半固形の脂肪分を指していたと思いますが、植物オイルに「バター」というネーミングを授けた人はエラい。
バターというネーミングからとても「安全」な印象を受けます。
「シアバター」というアフリカのシアの木がら採れるオイルは、はじめて聞いたときなんかとっても「おいしそう」に感じたものです。
しかし、この場合のバターは本来のバターやマーガリンとはまったく無関係です。
トイレタリーや化粧品の製品に多用される「モイスチャーミルク」「ミルクローション」などが本来のミルクとまったく無関係な事実と似ています。このへんはネーミングの勝利ですね。
ココアバターやシアバターの「バター」は植物オイルながら常温で白色固形や半固形状のものを慣用的に指す言葉になっています。さらに固くてベタつきが少ないと「ワックス」と呼ばれます。
分子的には、脂肪酸の炭素数(C)が多いもの(炭素数12以上の高級脂肪酸)でナンタラという難しい定義がありますが、一般にバターより固目の固形状オイルで、気化すると良く燃えるモノがワックスです。
それって日本語では、蝋燭(ロウソク)のロウに当たります。
本来のワックスは植物性・動物性ともにありますがもともと天然でした。蝋燭のロウも「ハゼの木」になる「ハゼの実」から採れる天然蝋(ワックス)でした。
ワックスといえば、自動車にかけるワックスや床板にかけるワックスなど最近ではケミカルをイメージさせるので、化粧品原料としては響きがよくありません。
その点「バター」は食べ物をイメージして安全なイメージです。練り香水も基材として有名なミツロウ(ビーワックス)も良いイメージを得るために「蜜バター」というネーミングに変えようと社内提案しましたが、あっさり却下されました。

(そのまま食べてしまいたくなる香り)
さて、ココアバターでハンドクリームを作ってみました。ココアバターは袋を破いただけで気が遠くなる甘さ。
こういう原料はグルマン系(お菓子系、もともとの意味はフランス語で「大食い野郎」)化粧品やグルマン・フレグランスにぴったりですが、あまりにも強烈で他には応用できそうにもありません。
やはり基材は無色・無臭が使いやすいですね。
もし商品化するとしたら、ハンドクリーム「ザ・カカオ」といった感じの商品にするのがいいかも。添加物もなしにすぐにできてしまいそうです。完全天然で保湿効果も抜群らしいです。
※「ココアバター」も「シアバター」も日本の化粧品原料名としては、正式なものではなく正式にははそれぞれ「ココア脂」「シア脂」となります。
(2007-10-09)
熱帯に生育する「カカオの木」には、大きな「カカオの実」が実ります。
「カカオの実」には「カカオ豆」が含まれます。つまり「カカオ豆」は「カカオの実」の種(タネ)です。
この種には豊富な脂肪分や食物繊維が含まれているそうです。カカオ豆を水に浸けて発酵させ種の皮と胚芽を取り除いてすりつぶした固形状にしたものが「カカオマス」になります。
カカオマスは「チョコレート」や「ココア」(ココアパウダー)の原材料です。同時に「ココアバター」が採れます。
なぜ「カカオ」(Cacao)が「ココア」(Cocoa)というネーミングに変化するか不明です。「カカオバター」でもよさそうですが、なにか理由があるのでしょう。
私は、街に出たときハーブ・野草のお店や、手作り化粧品原料を販売しているお店にぶらりと入ることがあります。先日御徒町を歩いていてぶらりと入ったお店でココアバターを見つけました。
ココアバターは食べ物の原材料ですが、そこでは「化粧品原料のコーナー」で販売されていました。
ハンドクリームか練り香にしてみるか、と手に取ってみるとココアバターはクリーム色。
「チョコレート色でない」
ところで、「バター」とはもともと牛乳から採れる動物性の半固形の脂肪分を指していたと思いますが、植物オイルに「バター」というネーミングを授けた人はエラい。
バターというネーミングからとても「安全」な印象を受けます。
「シアバター」というアフリカのシアの木がら採れるオイルは、はじめて聞いたときなんかとっても「おいしそう」に感じたものです。
しかし、この場合のバターは本来のバターやマーガリンとはまったく無関係です。
トイレタリーや化粧品の製品に多用される「モイスチャーミルク」「ミルクローション」などが本来のミルクとまったく無関係な事実と似ています。このへんはネーミングの勝利ですね。
ココアバターやシアバターの「バター」は植物オイルながら常温で白色固形や半固形状のものを慣用的に指す言葉になっています。さらに固くてベタつきが少ないと「ワックス」と呼ばれます。
分子的には、脂肪酸の炭素数(C)が多いもの(炭素数12以上の高級脂肪酸)でナンタラという難しい定義がありますが、一般にバターより固目の固形状オイルで、気化すると良く燃えるモノがワックスです。
それって日本語では、蝋燭(ロウソク)のロウに当たります。
本来のワックスは植物性・動物性ともにありますがもともと天然でした。蝋燭のロウも「ハゼの木」になる「ハゼの実」から採れる天然蝋(ワックス)でした。
ワックスといえば、自動車にかけるワックスや床板にかけるワックスなど最近ではケミカルをイメージさせるので、化粧品原料としては響きがよくありません。
その点「バター」は食べ物をイメージして安全なイメージです。練り香水も基材として有名なミツロウ(ビーワックス)も良いイメージを得るために「蜜バター」というネーミングに変えようと社内提案しましたが、あっさり却下されました。

(そのまま食べてしまいたくなる香り)
さて、ココアバターでハンドクリームを作ってみました。ココアバターは袋を破いただけで気が遠くなる甘さ。
こういう原料はグルマン系(お菓子系、もともとの意味はフランス語で「大食い野郎」)化粧品やグルマン・フレグランスにぴったりですが、あまりにも強烈で他には応用できそうにもありません。
やはり基材は無色・無臭が使いやすいですね。
もし商品化するとしたら、ハンドクリーム「ザ・カカオ」といった感じの商品にするのがいいかも。添加物もなしにすぐにできてしまいそうです。完全天然で保湿効果も抜群らしいです。
※「ココアバター」も「シアバター」も日本の化粧品原料名としては、正式なものではなく正式にははそれぞれ「ココア脂」「シア脂」となります。
(2007-10-09)
search